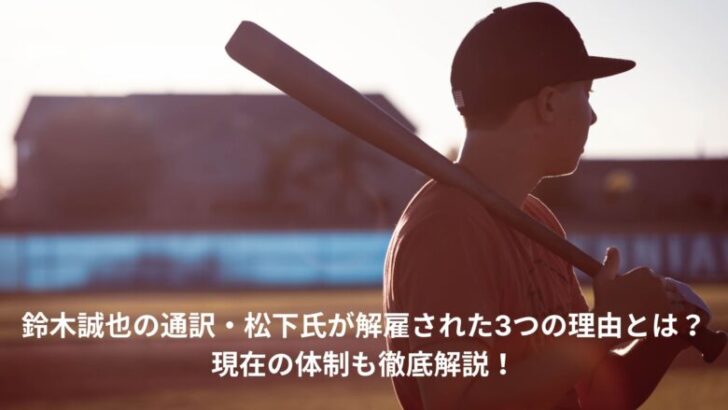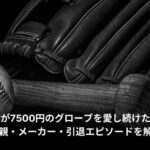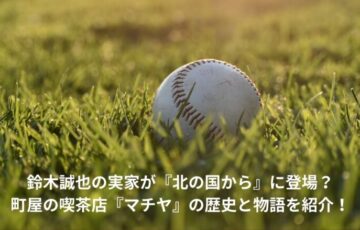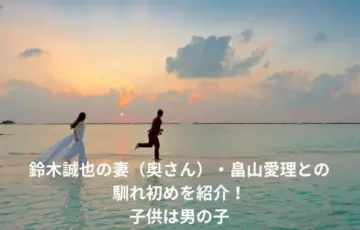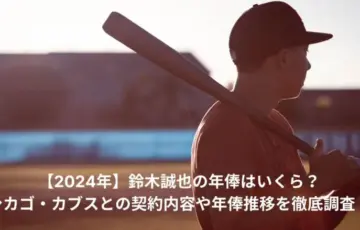メジャーリーグ・シカゴ・カブスの鈴木誠也選手と二人三脚で歩んできた松下登威氏の突然の解雇は、多くのファンに衝撃を与えました。
通訳という役割を超え、鈴木誠也選手の心の支えとなっていた松下氏がチームを去ることになった背景には、どのような事情があったのでしょうか。
本記事では、現地メディアや関係者の証言をもとに解雇の真相に迫るとともに、解雇後に構築された新たなサポート体制についても詳しく解説します。
言葉の壁を越えた真のパートナーシップとチーム戦略の狭間で起きた出来事から、メジャーリーグで戦う日本人選手を支える「影のチームメイト」の重要性が浮き彫りになります。
Contents
鈴木誠也の通訳・松下登威氏とはどんな人物か?
 画像引用元:Yahoo!ニュース
画像引用元:Yahoo!ニュース
2022年、メジャーリーグ・シカゴ・カブスに移籍した鈴木誠也選手とともに、多くのファンの注目を集めたのが、彼の専属通訳として同行した松下登威氏です。
表舞台に立つことは少ない存在ながら、選手にとって通訳は、言葉だけでなくメンタルや生活の支えとなる重要なパートナーです。
とくに異文化の中で戦う日本人選手にとって、通訳の存在がチーム内での立ち位置やパフォーマンスに大きな影響を与えることもあります。
ここではまず、松下氏がどのような経歴を持ち、鈴木誠也選手にどのように寄り添ってきたのかを見ていきます。
単なる通訳を超えた彼の役割が、どれだけ大きかったのかがわかるはずです。
通訳としての経歴と鈴木誠也との関係
鈴木誠也選手がシカゴ・カブスに入団したのは2022年。
そのタイミングで通訳としてチームに加わったのが松下登威(まつした・とうい)氏です。
松下氏は通訳としての専門的なスキルだけでなく、日本とアメリカの文化的な違いにも精通しており、鈴木誠也選手の生活面や精神面をしっかりサポートしてきました。
特に、メジャーリーグでは言葉だけでなく文化の違いからくる小さな誤解やストレスが積み重なることが多くあります。
松下氏はそうした場面で、単なる「翻訳」ではなく、意味や背景をていねいに伝える「橋渡し役」としての役割を果たしてきました。
鈴木誠也選手も松下氏に対して深い信頼を寄せていたと言われており、試合中の細かいやりとりやプライベートでの相談など、日常のあらゆる場面で欠かせない存在となっていました。
通訳という立場ながら、チームの一員としての信頼を得ていたことは、非常にめずらしく、また重要なポイントだと言えるでしょう。
通訳を超えた役割とチーム内での評価
松下氏が評価された理由は、ただの通訳としての仕事をこなしていただけではないからです。
彼は試合中も常に鈴木誠也選手の近くにいて、打席での内容や相手投手の特徴などをメモに取り、それを選手やチームと共有していました。
これは通訳の仕事としては一般的ではなく、自発的に行っていたことだと報道されています。
また、鈴木誠也選手のユーモアや元気な性格をチームにうまく伝えることで、クラブハウス内の雰囲気づくりにも貢献していました。
こうした「人間的なつながり」を作ることは、外国人選手が新しい環境になじむうえでとても大切なポイントです。
カブスの前監督であるロス氏も、松下氏が鈴木誠也選手のキャラクターをしっかりチームに伝えてくれることで、チーム全体がうまくまとまっていたと評価しています。
ファンからも、ベンチで一緒に戦っている姿や細かな気配りに対して、温かい声が多く寄せられていました。
松下登威氏が解雇された3つの理由
 画像引用元:中日スポーツ
画像引用元:中日スポーツ
鈴木誠也選手を支えてきた松下登威氏が、2024年シーズン途中でチームから解雇されたことは、ファンにも大きな衝撃を与えました。
正式な解雇理由について、カブス球団から明確な発表はありませんでしたが、現地メディアや関係者の証言から、いくつかの背景が浮かび上がっています。
ここでは、考えられる3つの主な理由について詳しくみていきます。
解雇理由①:コミュニケーション上の問題
松下氏の解雇について最も多く指摘されたのが、「コミュニケーション上の問題」です。
通訳は選手とチームをつなぐ重要な役割を担っていますが、特にメジャーリーグのように多国籍の選手が集まる環境では、ただ言葉を訳すだけでなく、空気を読む力や細かなニュアンスを正しく伝える力が求められます。
一部報道によると、鈴木誠也選手とチーム内での意思疎通にズレが生じる場面が増え、練習中や試合中の連携ミスが目立ってきたと言われています。
カウンセル監督は「技術的な問題ではない」とコメントしていますが、裏を返せば、チームがもっとスムーズなコミュニケーションを求めていたことを示しているとも考えられます。
こうしたズレが積み重なったことで、球団側は新たなサポート体制への切り替えを決断した可能性があります。
解雇理由②:外野でのミスとの関連性
鈴木誠也選手は2024年シーズン中盤、外野守備でのミスが目立つようになりました。
特に平凡なフライを捕り損なう場面があり、それが試合の流れを左右することもありました。
現地メディアは、こうしたミスに「コミュニケーションの問題」が影響している可能性を指摘しています。
外野手は、試合中に他の守備位置の選手やコーチと細かく連携を取る必要があります。
もし言葉の壁や情報伝達の遅れがあれば、守備位置のずれや判断ミスにつながることも十分ありえます。
鈴木誠也選手のポテンシャルは高く評価されている一方で、細かなミスが続くことに球団側が危機感を抱き、チーム全体のパフォーマンス向上を目指して通訳体制を見直したとみられています。
解雇理由③:チームが求めた新たな視点と変化
3つ目の理由として考えられるのは、「新たな視点と変化」の導入です。
カブスは、ただ成績を上げるだけではなく、チームの若返りや新しいスタイルの確立を目指しているといわれています。
そのなかで、選手サポート体制も変革の対象となりました。
松下氏が務めていた通訳スタイルは、鈴木誠也選手との信頼関係に重きを置いた非常にパーソナルなものでした。
しかし、チームはより客観的なデータ分析や、全体最適を重視する方向へシフトしつつあります。
そのため、サポート体制にも、より技術的・戦略的なアプローチを求めるようになったと考えられます。
結果として、選手にとってはつらい別れだったかもしれませんが、チームとしては未来を見据えた決断だった可能性が高いでしょう。
通訳交代によるチーム内への影響とは?
 画像引用元:スポニチSponichiAnnex
画像引用元:スポニチSponichiAnnex
松下登威氏の解雇は、鈴木誠也選手だけでなく、チーム全体にも少なからず影響を与えました。
通訳は単なる翻訳者ではなく、選手とチームをつなぐ大事な架け橋です。
その存在が急に変わることで、選手の心に揺れや戸惑いが生まれることもあります。
とくに、鈴木誠也選手にとって松下氏は、アメリカ生活のはじめから支えてくれた存在でした。
2年以上も一緒に過ごしてきたパートナーを突然失うことは、精神的な負担となったでしょう。
通訳交代後、鈴木誠也選手の成績には一時的な波が見られました。
これは、単なる調子の上下だけでなく、新しい通訳とのコミュニケーションに慣れるまで時間が必要だったことも影響していると考えられます。
また、チームメイトとのちょっとしたやりとりや、監督・コーチとのコミュニケーションにも、違和感が生じた可能性があります。
しかし、カウンセル監督は状況を冷静に受け止め、鈴木誠也選手へのサポート体制を強化する方針を示しました。
通訳体制を変えた後も、正本尚人氏やエドウィン・スタンベリー氏といった専門スタッフたちが、すぐに連携を取り、鈴木誠也選手が安心してプレーできる環境を整えています。
SNSやメディアでも、松下氏の解雇を惜しむ声と同時に、チームが前向きに変化しようとしていることを評価する意見が多く見られました。
ファンにとっても、鈴木誠也選手が環境の変化を乗り越え、さらに成長していく姿を見守る楽しみが増えたとも言えるでしょう。
現在の通訳体制はどうなっているのか?
松下登威氏の解雇後、鈴木誠也選手のサポート体制は大きく変わりました。
現在は、複数の専門スタッフが役割を分担しながら、鈴木誠也選手を支える形になっています。
通訳だけでなく、技術サポートやデータ分析、メディア対応まで幅広くカバーする体制が整えられています。
ここでは、現在鈴木誠也選手をサポートしている主なスタッフについて詳しく見ていきます。
正本尚人氏の役割と技術的サポート
 画像引用元:横須賀三浦リトルシニア
画像引用元:横須賀三浦リトルシニア
正本尚人氏は、カブスで長年ビデオコーディネーターを務め、環太平洋地域の担当も兼任しています。
現在は、鈴木誠也選手に対してフォームの乱れを細かくチェックしたり、試合中の動きを分析したりするしています。
単なる映像の管理だけではなく、映像を使って問題点を「見える化」し、改善点を選手に伝える役割を果たしています。
特にメジャーリーグでは、試合のスピードやプレッシャーがとても大きいため、こうした裏方の支えがパフォーマンス維持に欠かせません。
正本氏はダルビッシュ有選手がカブスに在籍していた時代から親しく、信頼されていた人物でもあります。
そのため、鈴木誠也選手にとっても安心できる存在になっていると考えられます。
エドウィン・スタンベリー氏のデータ分析とサポート
 画像引用元:full-Count
画像引用元:full-Count
エドウィン・スタンベリー氏は、もともと今永昇太投手の通訳を担当しているスタッフです。
しかし単なる通訳だけでなく、ストレングス&コンディショニング・コーチとしての知識も持っており、選手のフィジカル面のサポートや、パフォーマンス向上に役立つデータ分析も行っています。
鈴木誠也選手に対しても、野球のデータを使ったアドバイスや、試合前後の調整方法についてアドバイスを送る役割を担っています。
スタンベリー氏のように、通訳とアナリストの両方のスキルを持つ人物がサポートすることで、言葉だけでなく、より深い部分で選手とチームの橋渡しができるようになっています。
村田慎吾氏の通訳対応とメディア連携
 画像引用元:スポーツ報知
画像引用元:スポーツ報知
村田慎吾氏はソフトウェアエンジニアとしてチームに所属しているスタッフです。
通常はエンジニア業務が中心ですが、必要に応じて通訳としてもサポートを行っています。
特に、2025年に予定されている東京ドームでの開幕戦に向けたメディア対応では、鈴木誠也選手の通訳を担当しました。
大勢の報道陣が集まる中で、鈴木誠也選手の意図を正確に伝えるだけでなく、チームとの調整役もこなすなど、スムーズなコミュニケーションに貢献しました。
村田氏がいることで、通常の通訳体制に柔軟性が生まれ、急な対応が求められる場面でも安心できる環境が整っています。
まとめ
鈴木誠也選手の通訳だった松下登威氏は、単なる翻訳にとどまらない、選手とチームをつなぐ大切な存在でした。
しかし、チーム内でのコミュニケーションの問題や、外野でのミスの影響、新しい視点を求める球団の方針により、2024年シーズン途中で解雇されるという大きな転機を迎えました。
現在は、正本尚人氏、エドウィン・スタンベリー氏、村田慎吾氏の3名が役割を分担し、鈴木誠也選手をサポートする体制が整えられています。
技術サポート、データ分析、メディア対応まで幅広くカバーできる体制となり、これまで以上に組織的なサポートが期待されています。
異国の地でプレーを続ける日本人選手にとって、通訳やサポートスタッフはまさに「影のチームメイト」といえる存在です。今回の変化を乗り越えた鈴木誠也選手が、今後さらにたくましく成長し、メジャーリーグで大きな結果を残していく姿に注目が集まります。
今後も彼の活躍とともに、新体制の効果がどう表れていくのか、引き続き見守っていきたいところです。