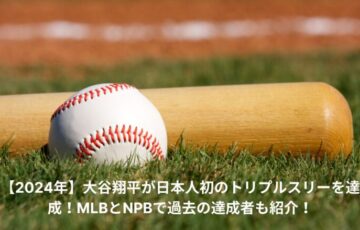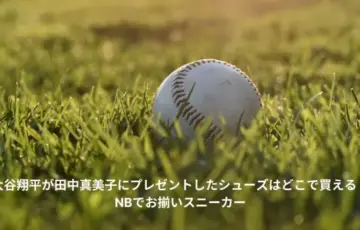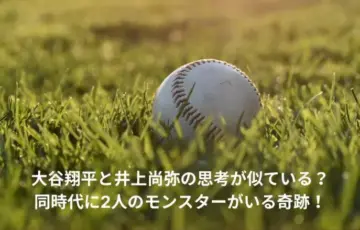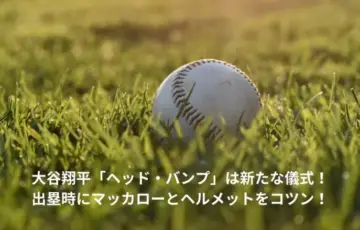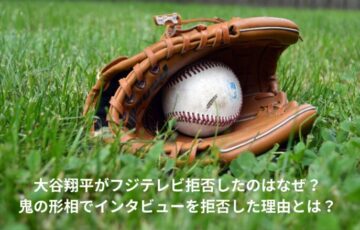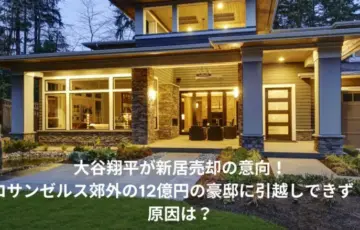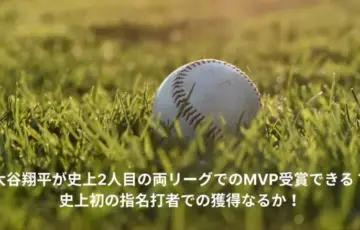「大谷翔平は英語が話せるのに、なぜ記者会見では話さないの?」「スピーチでは流ちょうなのに、普段は通訳を使っているのはどうして?」
大谷翔平選手が公の場で英語を話さないのは、語学力の不足ではなく、戦略的かつ文化的な理由が背景にあります。
この記事では、大谷翔平選手の実際の英語力やスピーチが称賛される理由を紹介しながら、彼が英語を“話さない”7つの背景要因について詳しく解説します。
証言や具体的な事例をもとに、誤解されがちな「英語を話さない」真意に迫ります。
Contents
大谷翔平の英語スピーチが絶賛される理由とは?
大谷翔平選手が行う英語スピーチは、短くても力強く、聞く人の心にしっかりと届くことで知られています。
そのスピーチは、ただ英語が話せるということ以上に、「伝える力」や「感情を込めた表現」によって、国内外のファンやメディアから高い評価を受けています。
では、実際にどのようなスピーチがあり、どこが評価されているのでしょうか?
以下では、具体的な内容と注目ポイントを見ていきましょう。
英語スピーチの内容と評価された表現
 画像引用元:full-Count
画像引用元:full-Count
2024年11月、ドジャースの優勝パレード後に行われたスピーチでは、「This is so special moment for me.(私にとってとても特別な瞬間です)」「I’m so honored to be here and to be part of this team. Congratulations Los Angeles. Thank you fans!(このチームの一員になれ、とても名誉に感じています。ロサンゼルス、おめでとう。ファンの皆さんありがとうございます!)」という言葉が注目を集めました。
このスピーチは、難しい単語を使わず、シンプルでわかりやすい言葉で構成されており、大谷翔平選手の素直な気持ちがまっすぐ伝わる内容でした。
さらに、2025年1月の全米野球記者協会(BBWAA)主催の夕食会では、山火事の被災者に向けた思いやりのこもったメッセージを英語で届けました。
最後の「Stay strong and united. We will get through this.」という一言は、多くの人々に勇気を与え、スピーチの締めくくりとして強い印象を残しました。
専門家やファンによる高評価のポイント
英語教育や通訳の専門家たちは、大谷翔平選手の発音について「非常に自然でネイティブに近い」と評価しています。
とくに日本人が苦手とする「th」や「a」の音もしっかりと発音されており、実践的な英語力の高さがうかがえます。
また、「shoutout to」など、日常でよく使われるカジュアルな表現も取り入れられており、自分の言葉で話している印象を強く与えています。
ファンの間でも「どんどんうまくなっている」「話し方に気持ちがこもっている」といった好意的な声がSNSなどで多く見られます。
チームメイトが語る大谷翔平の英語力の実態
 画像引用元:President
画像引用元:President
大谷翔平選手は、公式の場では通訳を通して日本語で話すことが多いものの、実際にはチーム内で英語による会話を積極的に行っています。
チームメイトたちの証言からは、予想以上に高い英語理解力と、スムーズなコミュニケーション能力がうかがえます。
英語での会話・冗談ができるレベル
親友であるサンドバル投手は、「大谷がチームメイトを爆笑させたジョークがある」と語っており、大谷翔平選手が英語のユーモアを理解し、それを自ら発信する力があることを示しています。
また、ロバーツ監督も「彼のユーモアはチームの中でも際立っている」とコメントしており、英語によるやりとりが自然に行われている様子が伝わってきます。
英語での軽い冗談や会話が交わせるという事実は、大谷翔平選手の英語力が単なる「聞き取り」だけでなく、「実践」に活かされていることの証でもあります。
数値評価と英語スキルのバランス
内野手のダビッド・フレッチャー選手は、大谷翔平選手の英語力を「10段階で6.5」と評価しています。
その内訳は、「理解力が9、話す力が4.5」とされており、リスニング力の高さが際立っていることがわかります。
さらに、マックス・マンシー選手は「大谷は努力家で、英語での会話も自然にできる。話していると、言葉の壁を忘れてしまうことがある」と語っており、彼の英語力がチーム内で信頼されている様子がうかがえます。
こうした証言は、大谷翔平選手が日常的に英語を使いこなしていること、そしてその努力と成果がチームメイトにも広く認識されていることを物語っています。
大谷翔平が英語を話さない理由
 画像引用元:Number
画像引用元:Number
これほど高い英語力を持ちながら、大谷翔平選手が記者会見やインタビューなどの公式の場で英語を話さないのはなぜなのでしょうか。
それは単なる苦手意識によるものではなく、プロとしての戦略的かつ多面的な判断があるからです。
ここでは、その理由を大きく2つの視点から解説していきます。
報道リスクやファン・スポンサーへの配慮
大きな理由のひとつは、「誤解を避けるため」です。
大谷翔平選手ほどの注目度になると、たった一言でもメディアに大きく取り上げられる可能性があります。
英語での表現が不完全だった場合、意図しない形で発言が伝わってしまうリスクもあるため、正確な情報を届けるために通訳を通す選択をしているのです。
また、日本のファンにしっかり伝えるという目的もあります。
日本語を使うことで、すべてのファンに等しくメッセージを届けることができるからです。
さらに、スポンサーの意向も影響していると考えられます。
「完璧なイメージ」を保つため、通訳を通した方が安全であり、企業ブランドと本人の価値を守ることにつながります。
メンタル・文化的背景とメディア戦略
もうひとつの視点は、日本人としての文化的な価値観やメンタル面にあります。
日本では「完璧にできないことを恥ずかしいと感じる」風土があり、大谷翔平選手も「初対面の人には正しい英語で自分の考えを伝えたい」と語っています。
このような慎重な姿勢は、単に言葉の問題ではなく、「誤解なく伝える責任感」の表れでもあります。
また、通訳を使うことで発言の意図を正確にコントロールでき、記者やメディアからの突発的な質問にも安全に対応できます。
これは英語力の問題ではなく、アスリートとして冷静にリスクを見極めた上での判断といえるでしょう。
英語を使う場面と語学習得への努力
 画像引用元:Yahoo!Japan
画像引用元:Yahoo!Japan
公の場では通訳を通すことが多い大谷翔平選手ですが、実際には多くの場面で英語を使いこなしています。
その裏には、日本時代から積み上げてきた地道な努力と、アメリカ移籍後の継続的な学習があります。
ここでは、大谷翔平選手が英語を使っている具体的なシーンと、語学習得への取り組みについて紹介します。
英語を使っている実例とその反響
2025年3月、ドジャースのクラブ会員向けに贈られた記念の盾を受け取った際、大谷翔平選手は「This is cool. You know? I want to get this again and again.」と自然な英語でコメントしました。
この様子はSNSで拡散され、「英語がうまくなっていて驚いた」「とても流ちょうだった」といった反応が多く見られました。
また、ESPNの番組では、通訳を介さず自らのシューズについて英語で説明する場面もありました。
さらに、マックス・マンシー選手に対して、打席での動きについて身振りを交えて英語で伝えたこともあり、現場で実践的に英語を使っている様子がわかります。
このように、英語でのやりとりは日常的になっており、通訳なしでもスムーズに会話できる信頼関係が築かれているのです。
日本時代からの学習姿勢と現在の取り組み
大谷翔平選手は、高校卒業後にすぐメジャー挑戦を視野に入れていたため、早くから英語学習に力を入れていました。
日本ハム時代には、外国人選手との英語での会話を積極的に行っていたと言われています。
アメリカに移籍してからは、専属通訳の水原一平氏と2時間以上のマンツーマン英語レッスンを続け、わからない単語や表現をすぐにメモし、実際の会話で使うことを繰り返してきました。
2024年に水原氏が退任して以降は、より自立的に英語を使うようになり、その変化は周囲にも明らかです。
勉強を続けながら、日々のやりとりの中で英語を磨いている姿勢は、多くのファンにも刺激を与えています。
まとめ
大谷翔平選手の英語力は、単に「話せるかどうか」では語りきれません。
必要な場面ではしっかりと英語を使い、ファンや関係者の前では自分の言葉で思いを伝えています。
その姿は、多くの人に勇気を与え、「伝えることの本質」を体現しているように見えます。
それでも通訳を介するのは、発言が持つ影響力の大きさを理解し、誤解を避けるための判断であり、同時に日本のファンやスポンサーへの配慮でもあります。
「英語を話さない=英語ができない」という単純な見方ではなく、「正確に、誠実に伝えるためにどうするか」を考え抜いた結果といえるでしょう。
また、大谷翔平選手は「語学も勉強も、特別得意だったわけではない」と語りながらも、日々コツコツと学習を続けてきました。
机に向かって勉強し、現場で実践しながら英語力を伸ばしてきたその姿勢は、英語を学ぶ多くの人にとっての大きなロールモデルです。
これからも彼がどんな場面で、どのように英語を使っていくのか。
「話すかどうか」だけではなく、その背景や思いに目を向けることで、大谷翔平選手の本当の魅力がより深く見えてくるのではないでしょうか。